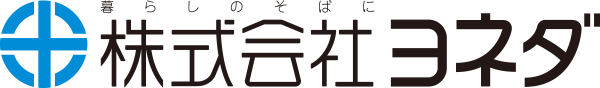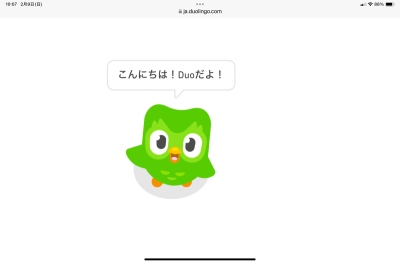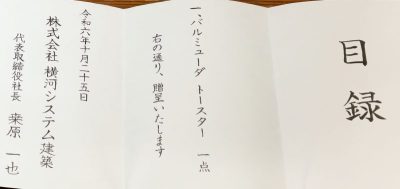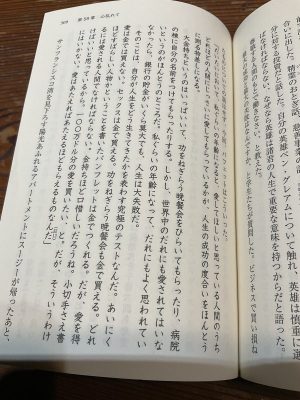過日、大阪の京橋にある山王美術館に行ってきました。大きなホテルチェーンの経営者が蒐集された日本画や洋画を見ることができました。美術館の横にあるロココ調?のホテルは以前弊社のF君が結婚式を挙げたホテルでした。当日のイベントは「エコール・ド・パリ展」でした。








思っている以上にコレクションが充実しており、鑑賞者も多くなくゆっくりと観ることが出来ました。横山大観の絵やキスリングの絵が良かったです。帰りにミュージアムショップの横に簡単な休憩スペースがあり無償で珈琲を飲むことが出来ました。入場料も安価で申し訳ないような気分でした。
その後北浜にある適塾に行ってきました。蘭学者であり蘭方医学を学んだ緒方洪庵の私塾です。天然痘の治療を日本で先駆けて行いました。適塾では全国から集まった多くの若者に蘭学を教えました。適塾から福澤諭吉、大鳥圭介、橋本左内、大村益次郎、長与専斎など幕末から明治維新にかけて活躍した多くの人材を輩出しました。近所のお客様にご挨拶をした帰りに適塾の前を通り「行ってみよう」と思った次第です。







『虎狼痢治準』安政5年(1858年)のコレラ流行時に西洋の医書を参考に書かれた治療手引き書。医師に百冊無料配布。
『病学通論』日本最初の病理学書(Wikipediaより)
洪庵の私塾・適塾がどんなところかと言いますと塾頭を務めた福沢諭吉の「福翁自伝」の中に生き生きと描かれています。
「塾生の勉強」・・学問勉強ということになっては、当時世の中に緒方塾生の右に出るものはなかろうと思われるその一例を申せば私が安政三年の三月に、熱病を煩うて幸い全快に及んだが、病中は括り枕で、座布団か何かを括って枕にしていたが、追々元の体に回復してきたところで、ただの枕をしてみたいと思い・・・、枕がない、どんなに捜してもないと言うので、ふと思いついた。これまで倉屋敷に一年ばかり居たが、ついぞ枕をした事がない、と言うのは時は何時でも構わぬ、殆んど昼夜の区別はない、日が暮れてから寝ようとは思わず、しきりに書を読んでいる。読書に草臥れて眠くなってくれば、机の上に突っ伏して眠るか、あるいは床間の床側を枕にして眠るか、ついぞ本当に布団を敷いて夜具をかけて枕をして眠るなどと言うことはただの一度もした事がない・・これは私一人が別段勉強生でも何でもない、同窓生は大抵みなそんなもので、およそ勉強ということについては、実にこの上為しようはないというほどに勉強をしました。
「料理茶屋のものを盗む」・・緒方の書生は本当に万引きをしていたその万引きは呉服店で反物なんと念の入ったことではない、料理茶屋ので飲んだ帰りに、猪口だの小皿だの、いろいろ手頃な品をそっと盗んで来るような万引きである。同窓生互いにそれを手柄のようにしているから送別会などという大会の時には獲物も多い・・「君たちがそんな半端も物を挙げてくるのはまだ拙い。俺の獲物を拝見し給え」・・。
「難波橋から小皿を投ず」・・夜十時過ぎになって「嗚呼飲みたい」と一人が言うと「僕もそうだ」というものが、すぐ四、五人できた。ところがちゃんと門限があって出ることができぬから、当直の門番を脅迫して、無理に開けさして、鍋島の浜と言うの葦簀張でまずいけれども、芋蛸汁か何かで安い酒を飲んで、帰りに例の通りに小皿を五、六枚あげてきた。夜十二時過ぎでもあったか、難波橋の上に来たら、下流の方で茶船に乗って、ジャラ〃三味線を鳴らして騒いでるやつがある。「あんなことをしてやがる。こっちは百五十かそこらの金を見つけ出して、ようやく一盃を飲んで帰るところだ。忌々しい奴らだ。あんな奴があるから、此方等が貧乏するのだ」と言い様、私の持ってる小皿をニ、三枚投げつけたら、一番しまいの一枚で三味線の音がぷっつりやんだ。その時は急いで逃げたから・・・。塾の一書生が北の新地に行ってどこかの席で芸者に逢うた時に芸者が「世の中には酷い奴もある。橋の上からお皿を投げて、ちょうど私の三味線のにあたって裏表の皮を打ち抜きましたが、本当に危ないことでまずまず怪我をせんのが幸せでした・・」・・私どもはそれを聞いて、下手人にはちゃんと覚えがある。けれども、言えば面倒だから、その同窓の書生にもその時は隠しておいた。
「桃山から帰って火事場に働く」・・塾中兎角貧生が多いので、料理茶屋に行って旨い魚を買う事はまず難しい。夜になると天神橋か天満橋の橋詰に魚市が立つ。まぁいわば魚の残物のようなもので、値が安い。それを買ってきて手水盥で洗って、机の壊れたのか何かをまな板にして、小柄を持って揃えるような事は毎度やっていたが、私は兼ねて手の先が利いてるから、いつでも魚洗いの役目が回っていた。これは三月桃の花の時節で、大阪の城の東に桃山と言うところがあって、盛りだと言うから花見に行こうと相談ができた・・、例の通り、前の晩に魚の残物を買ってきて、その他氷豆腐だの、野菜物だの整えて、朝早くから起きて、早々に揃えて、それを折りか何かに詰めて、それから酒を買って、およそ十五人も同伴があったろう、弁当を順持ちにして桃山に行って、散々飲み食いいい加減になってるその時に下ふと西の方を見ると、大阪の南に当たって大火事だ・・・ちょうどその日に長与専斎が道頓堀の芝居を見に行ってる。我々花火連中は何も大阪の火事に利害を感じる事は無いから、焼けても焼けるでもどうにでも構わないけど、長与が行っている。もしや長与は焼け死にはせぬか・・・、とても探すわけにはいかぬ。まもなく、日が暮れて夜になった。もう夜になっては、長屋の事は仕方がない。「家事を見物しようじゃないか」と言って、その火事の中へどんどん入っていった。ところが荷物を片付けるので大騒ぎ。それからその荷物を運んでやろうと言うので、夜具か何の包みか、風呂敷を担いだり、箪笥を担いだり、なかなか働いて、だんだん進んでいくと、その時大阪では、焼ける家の柱に綱をつけて、家を引き倒すと言うことがある。その綱を引っ張ってくれと言う。「よし来た」とその綱を引っ張る。ところが、握り飯を食わせる、酒を飲ませる。如何も堪えられぬ面白い話だ。散々酒を飲み握り飯を食って、八時ごろにもなりましたろう。それからいちど塾に帰った。ところがまだ焼けている。「もう一度行こうではないか」とまた出かけた・・。
「工芸技術に熱心」・・今日のように全て工芸技術の種というものがなかった。蒸気機関などは日本国中で見ようと言ってもありはせぬ。科学の道具にせよ、どこにも揃ったものはありそうにもしない。揃ったものどころではない、不完全な物もありせぬ。けれども、そういう中にいながら、器械のことにせよ、科学のことにせよ大体の道理は知っているから、どうかして実地を試みたいものだと言うので、原書を見てその図を写して似寄りのものを揃えるということについてはなかなか骨を降りました・・・それから今度は碯砂(ドウシャ)製造の野心を起こして、まず第一の必要は塩酸アンモニアであるが、これはもちろん薬店にある品物ではない。そのアンモニアを作るには、どうするかと言えば、骨ー骨よりももっと世話なしにできるのは、鼈甲屋などに馬爪の削屑がいくらでもあって、只でくれる。肥料にするかせぬか、わからぬが行きさえすればくれるから、それをどっさりもらってきて、徳利に入れて、徳利の外に土を塗り、また素焼きの大きな瓶を買って七輪にして、沢山火を起こし、その瓶の中に三本も四本も徳利を入れて、特に徳利の口には瀬戸物の管をつけて、瓶の外に出すなどいろいろ趣向して、どしどし火を仰ぎ立てると、菅の先からたらたら液が出てくる。すなわち、これがアンモニアである。至極うまく取れる事は取れるが、ここに難渋はその臭気だ。臭いも臭くないも、何とも言いようがない。あの馬爪、あんな骨類を徳利に入れて、蒸し焼きにするのであるから、実に鼻持ちならぬ。それを緒方の塾の庭の狭い所でやるのであるから、奥でももってたまらぬ。奥で堪らぬばかりではない。さすがの乱暴書生も、これには辟易してとてもいられない。夕方湯屋に行くと、着物が臭くって犬が吠えると言うわけ。例えば、裸でやっても、身体が臭いと言うて人に嫌がられる。もちろん製造の本人ではどうでもこうでも碯砂と言うものをこしらえてみましょうと言う熱心があるから、臭いのは何も構わず、頻りに試みてみるけど、なにぶん周辺の者が喧しい。下男下女までも胸が悪くてご飯が食べれないと訴える・・・鶴田仙庵らは思い切ったが、ニ、三の人は尚遣った。どうしたかと言うと、淀川の一番粗末な船を借りて、船頭を一人雇って、その船に例の瓶の七輪を積み込んで舟中で、今の通りの匂いの仕事をやるわ宜いが、やっぱり煙が立って、風が吹くと、その煙が陸の方に吹き付けられるので、陸の方で喧しく言う。喧しく言えば、船を動かして、川を登ったり、降ったり、川上の天神橋、天満橋から、ずっと下の玉江橋の辺まで、上下に逃げて回ってやったことがある・・・。
「自身、自力の研究」・・さて、その写本の物理書医書の解読をどうするかと言うに、講釈の為手もなければ、読んで聞かしてるくれる人もない。内緒で教えることも聞くことも、書生間の恥辱として、万々一もこれを犯すものはない。ただ一人でもってそれを読み砕かねばならぬ。読み砕くには、文典を土台にして辞書を頼るほかはに道はない。その辞書と言うものは、ここにズーフと言う写本の辞書が塾に一部ある。これはなかなか大部なもので、日本の紙でおよそ三千枚ある。これを一部こしらえると言う事は、なかなか大きな騒ぎで容易にできたものではない。これは昔、長崎の出島に在留していたオランドのドクトル・ズーフと言う人がハルマと言うドイツオランダ対訳の原書の字引を翻訳したもので、蘭学社会唯一の宝書と崇められ、それを日本人が伝写して、緒方の塾中にもたった一部しかないから、三人も四人もズーフの周囲に寄り合って見ていた・・・ズーフでわからなければウェーランドを見る。ところが初学の間はウェーランドを見てもわかる気遣いは無い。それ故、便るところはただズーフのみ。会読は、十六とか三八とか大抵日が極まっていて、いよいよ明日が会読だと言うその場は、いかな懶惰生でも大抵眠る事は無い。ズーフと言う字引のある部屋に五人も六人も群をなして、無言で地引を引きつつ勉強している。それから翌朝の会読になる。解読をするも籤でもって、ここからここまでは誰と決めてする。会頭はもちろん原書を持っているので、五人なら五人、十人なら十人、自分に割合られたところを順々に講じて、もしその人ができなければ次に回す・・。
「大阪書生の特色」・・江戸と大阪とおのずから事情が違っている。江戸の方では、開国の初とは言いながら、幕府を始め、諸大名の屋敷というものがあって、西洋の新技術を求めることが広く、且つ急である。したがって、いささかでも洋書を解すことのできるものを雇うとか、あるいは翻訳をさせれば、その返礼に金を与えるとか言うなことで、書生輩がおのずから生計の道に近い。ごく都合の良いものになれば、大名に抱えられて、昨日までの書生が今日は何百石の侍になった言うことも稀にはあった。それに引き換えて、大阪はまるで町人の世界で、何も武家と言うものは無い。したがって、砲術をやろうと言うものもなければ、原書を問い調べようと言うものもあり。それ故、緒方の書生が幾年勉強して何ほど偉い学者になっても、とんと実際の仕事に縁がない。すなわち、衣食に縁がない。縁がないから、縁を求める言うことにも思い寄らぬので、しからば何のために苦学するかと言えば、一寸と説明は無い。頓と自分の身体はどうなるであろうかと考えたこともなければ、名を求める気もない。名を求めるどころか、蘭学諸生と言えば、世間に悪く言われるばかりで、既に己に焼けになっている。ただ昼夜苦しんで六しい原書を読んで申し面白がっているようなもので、実に訳のわからぬ身の有り様とは申しながら、一方進めて、当時の書生の心の底を叩いてみれば、おのずから楽しみがある。これを一言すれば➖西洋日進の書を読む事は、日本国中の人にできないことだ、自分たちの仲間に限って、このようなことができる、貧乏しても難渋をしても、粗衣粗食、一見見る影もない貧書生でありながら、智力思想の活発高尚なる事は、王侯貴人も眼下に見下すと言う気位で、ただ六かしければ面白い、苦中有楽、苦即楽という境遇であったと思われる。例えばこの薬は何に効くか知らぬけれども、自分たちより他にこんな苦い薬をよく飲むものはなかろうと言う見識で、病の在るところにも問わずに、ただ苦ければ、もっと飲んでやる位の血気であったに違いない・・・
「新訂 福翁自伝」福沢諭吉著 より
・・以前此本を読んで話が面白く抱腹絶倒しました。それと江戸時代末期にこんなにも合理的な人が居たのかと感心する事しきりでした。福沢諭吉の書いた当時のベストセラー「学問のすゞめ」は初版(明治5年)で20万部、最終的には300万部売れたそうです。