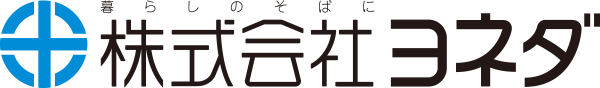2024年9月19日
厳しい暑さが続きます。
お盆休みに時間があるので以前に読んだ「W・チャーチル わが半生」中村祐吉訳と「第二次大戦回顧録抄」ウィストン・チャーチル著 毎日新聞社翻訳を読み返しておりました。

W・チャーチルは1974年英国のオックスフォードシャーで公爵家の子供として生まれます。広大な領地を持ち「貴族の中の貴族」として生まれます。父は保守党の政治家、母は米国も著名なウオール街の投機家の娘でした。父の知名度により名門ハロー校に進みますが「落ちこぼれ」でラテン語などは全くできませんでした。気分にムラがあり忘れ物や提出物の遅れ等で学校では校長から二度の鞭打ちの刑に晒されたりします。幼児の時に1500個のおもちゃの兵隊を持っており軍事教練等に強く興味を持つ様になります。三度の受験でサンドハースト王立陸軍士官学校へ入学。成績も悪かったために歩兵士官候補生にはなれず騎兵士官候補生になります。ポロ用の馬の費用もかかり騎兵は人気がありませんでした。晴れて地形学、戦略、戦術、地図、戦史、軍法、軍政など自分のの興味ある分野の学習に力を注ぐ様になります。卒業時には130人中20位の好成績で卒業しオルダーショット駐留の軽騎兵第4連隊に配属されます。
そこからが彼の飽く事なき冒険心、行動力が発揮されます。連隊に配属された時にビクトリア朝末期で10年間は大きな紛争もなく無事泰平の世が続いていました。チャーチルは実戦に参加した先人の話を聴き入るうちに自分も「砲火をくぐり抜けた」経験を強く欲する様になります。
当時キューバでスペイン軍とキューバ反乱軍の長期ゲリラ戦が重大局面に入っていました。父は亡くなっていましたが様々な名門の人脈を辿って紹介状を得てハバナ(キューバ)へ出発。現地では無事戦火をくぐりました。その後インドに駐留することになりインドでは王侯貴族の様な生活をしポロ競技の訓練、試合に熱中します。インドは平穏だった為チャーチルは本国の母に送ってもらいアリストテレスの『政治学』、プラトンの『共和国』、ギボンの『ローマ帝国衰亡史』、マルサスの『人口論』、ダーウィンの『種の起源』など多くの名著、古典に親しむ様になりました。その間も実戦に参加すべく許可を得るために自分の隊と本部の間を二千哩(マイル、3200km)を炎暑を冒して往復します。そしてマラカンドの戦いに参戦します。又、並行して新聞社の報道員を嘱託されます。出版された「マラカンド野戦軍」は評判となり時の皇太子、後のエドワード7世から祝意の手紙を頂いたりします。
エジプト(英国の傀儡政権)、スーダンの紛争では総司令官キッチナーから従軍を拒否されるが、首相ソールズベリに嘆願したり参謀本部に哀訴して砂漠の戦いに参戦します。この戦いでも「デイリーテレグラフ誌」の特派員を兼ね戦争通信を送り続けます。後の「ナイル河畔の戦い」も評判の書籍になります。実家が名門で付き合いも多く実質的には年々債務がかさんでおり、自分自身の活動範囲の広さ、騎兵として薄給で馬2頭も維持し、制服も高価故文筆や著述家としての講演でお金を稼ぐ様になります。心の中には父がそうであったように議会に入る野心も持つ様になります。
英国は南アフリカにも権益があり、南アフリカでのボーア人との戦いでは一旦軍を退役しながら、新聞特派員として戦地に向かいました。戦闘に参加してボーア軍の捕虜になり、持ち前の知恵と勇気によって脱走し国境まで300哩(480km)を夜間歩きながら目指しました。運良く英国人の炭鉱の支配人に匿ってもらい貨車の荷物の中に潜んで隣国へ脱出し英国で一躍戦意高揚の英雄となりました。
・・ダーバンに着くと、私はいつの間にか英雄として祭り上げられている自分自身を見出した。港は旗をもって飾られ、楽隊、民衆が埠頭を埋め、提督、将軍が握手を求める。その熱烈さに私はまさに寸断されんばかりであった・・・(本書より)
チャーチルは三度四度死地に突入し九死に一生を得ていますがまたぞろ弾丸の中へ飛び出していきます。本書の中に「20歳から30歳までの年月が私にとり、・・・・その精彩さにおいて、千変万化の劇しさにおいて、奮闘努力という点において、他の何よりも優っている。青年よ、決して現状に甘んじるなかれ、地球は君のもの、その上森羅万象も皆君のものだ・・」こうしたチャーチルの積極性、努力突進は、しかしながら、一方に敵をつくりました。生意気、無遠慮、無謀のそしりを彼は受けました。「『若いチャーチルに必要なのは規律と訓練であるとか、勲章あさり、自家広告家』・・・などと言う言葉を浴びせかけられ自分の進もうとする行く手には何時も障害が起こった」などと記しています。
チャーチルはボーア戦争帰国後保守党から出馬し下院議員に当選します。そこまでの歴史がW・チャーチルの「我が半生」に書かれています。ヨハネスブルクからの帰国時コプエス停車場での近くで土手の近くでボーア軍の砲弾が炸裂しました。
・・・この2インチのクルーサット砲弾こそ私が修羅場で見る最後の砲であろうと。しかしこの期待が誤っていたことは後でわかった。・・(本書より)
「第二次大戦回顧録」(のちにこの本によりW・チャーチルはノーベル賞文学賞を受賞)は全6巻からなり日本語訳は24巻、その中から日本に関係ある部分を「抄」として纏めてあります。
第一次大戦を最後の戦争として終止符を打とうととした戦勝国はベルサイユ講和条約中の、対独制裁条項の盲点をドイツに利用されます。再軍備したドイツがヒトラーの大胆不敵な攻勢によってヨーロッパ制覇に乗り出します。その中でアジアでは日本が局地的混乱を口実に奉天と満鉄沿線を占領。米国の敵視政策によって日本は国際連盟を脱退。マレー半島、シンガポール、香港にも攻撃を受けアジアにも大きな版図を持つ英国戦時内閣を率いるW・チャーチルの苦慮する様が書かれています。
W・チャーチルは国会議員となり第一次大戦では海軍大臣、軍需大臣として参画、その後作戦の失敗の責任を取る形で辞任、一中佐としてフランス戦線に赴きました。第二次大戦では対独宣戦布告後2時間後には海軍大臣として迎えられその後戦時内閣の首相として英国を率いるようになります。
・・・六時に参内せよとの知らせが私のところに来た。私は直ちに国王の所に招かれた。国王はほほえみながら、「あなたに組閣をお願いしたいのですが」と言われた。私は喜んでお引き受けすると申し上げた。・・。
・・・かくして5月10日夜、私は一大非常時に一国の首相として権力を握った。その権力をその時からこの世界大戦の五年三ヶ月にわたって保った。われわれの政権末期にわれわれの敵は全て降伏し、あるいはまさに降伏戦とする時、私はイギリス国民から国事指導の役割を解かれた。
ついに私は、全分野にわたって指令を発する権力を持った。私は運命と共に歩いている気がした。私には戦争のことなら、なんでも知っている自信があった。私の生涯のすべては、ただこの時、この一大試練のために準備されたものであると気がした・・(いずれも本書より)
「われわれはわれわれの国を守り抜く、どれだけの犠牲があろうと、
海浜で、上陸地点で、街路で、丘で戦い抜く。
われわれは断じて降伏しない。
万一 ―― そのようなことをわれわれは一瞬たりとも信じないが ――、
本土の大部分が征服され、人々が飢えに苦しむことがあっても、
イギリス艦隊の兵力の援護を受けた海のかなたのわが帝国(英連邦)が、
権力と武力をすべて備えた新世界(アメリカ)が旧世界の救済と解放に駆けつけるまで、
必ずや戦い抜くであろう」 (W・チャーチル演説)


ついでに新聞で見かけて購入していた「ダウニング街日記:首相チャーチルのかたわらで」(上下)ジョン・コルヴィル著 都築忠七他訳も読み進む。
著者のジョン・コルヴィルは貴族の家系、富、王室はじめ多くの縁故に恵まれ、高度の知性と学問的才能をもつ人物でありました。素晴らしい個性的魅力と身についたマナーの良さ、王権、祖国、国教会への強烈な忠誠心を備えておりました。時期によって王室の侍従、外務省役人、三人の首相(チエンバレン、チャーチル、アトリー)の秘書官補佐、チャーチルについては主席秘書官の一人、イギリス空軍の戦闘機パイロット、外為為替と証券発行を業務とするマーチャントバンカー等として活躍しました。
英国最大の試練の時にチャーチルやチャーチル婦人と常に時を共にします。又、独軍のロンドン大空襲もありながらも、友人と会食したり、乗馬やテニス、クロッケーなどを楽しみ文化的な時間も過ごします。食事を終わった後にはブリッジやバックギャモン(ボードゲーム)などにもこうじます。首相チャーチルも軍の要人や政治家も常時招いて会食を行います。「チエルシー」の地名が再三出てきますが今はテムズ側北岸の高級住宅街ですがそこに来客を迎える施設があった様です。国内の様々な軍施設、工場などの視察、フランスやヨーロッパの同盟国との切羽詰まった会談にも飛行機で行き来します。流石に七つの海を制覇した大英帝国の様に思います。
・・・6月25日火曜日 シールとトラベラーズで会食。結構快適な夕食だった。シールは、首相就任以来ウィストンは如何に様変わりしたかという興味深い説明をした。首相は冷静さが増し、乱暴さが控えめになり、荒々しさもひかえめになり、血の気が少なくなった。シールはこう考えている。自分の使命はわが国を目下の苦難から救うことだと信じており、その目的を達成するためなら、必要ならば、間違いなく自分の命を投げ出すはずだ。ウィストンは迷信深い。ロイヤル・オウクは11月13日金曜日の日没時に撃沈されたが、この日ウィストンは何時もの水たまり模様のネクタイではなく、ブラック・タイを間違ってつけていた。この事実をウィストンは極めて重視しているとのことである・・
・・・6月27日 木曜日 10時ごろ首相の寝室に行った。首相は赤いガウンを着て、葉巻を吸い、ミセス・ヒルに向かって何か口述していた、女史はタイプライターを前にしてベットの裾に座っていた。半分ほど書類が入っている首相用のメモ・ボックスがベットの上で口を開け、主将の脇にはクロムメッキの痰壺があった。ペットの黒猫ネルソンは、十番以前の黒猫にすっかり取って代わり、ベットの脚元で寝そべっていた。ウィストンはときどき目を細めてネルソンを眺めては、「かわいい猫だ」と言っていた・・・フランスとアルジェリアでは、イギリス嫌いのムードが大規模に広がっている。その一因はペタン政府に対するウィストンの厳しい批判であり、イギリスがフランスに十分な支援を与えなかったと言われている事もその一因である。イギリスでもフランス嫌いがさらに大規模に広がっている。これが和親協商の最終的な帰結なのだ。アメリカは落胆しフランス敗退の責任をイギリスになすりつける傾向があり・・
(ダウニング街日記:首相チャーチルのかたわらで」(上)ジョン・コルヴィル著 より)
この日記を読むことで「第二次大戦回顧録 抄」がある程度わかりやすく伝わってきます。切羽詰まった状況での判断や人間の考えている事、大袈裟に言えば哲学も感じられます。勿論英国からみた日本も見えるわけで「随分強かった」と思います。
何故「W・チャーチル 我が半生」を読もうと思ったのは少し前に「ドラッガー 我が軌跡 知の巨人の秘められた交流」P.Fドラッガー著を読んだからかもしれません。この本自体は非常に興味深く知的好奇心をかきたてられ一気に読みました。但し他のドラッカーの著書は非常に難解で読み解くことが難しいです。本書を読むことによりドラッカーの生きた「時代の空気」を知りたかったかもしれません。
アメリカで1939年に出版されたドラッガーの処女作であり経営三部作の第一作『「経済人の終わり』-全体主義は何故生まれたか』は社会に大きなインパクトを与えましたが、後に英国首相ウィストン・チャーチルに絶賛されました。彼はタイムズに書評を書いてくれただけでなく、首相就任後陸軍の幹部候補生学校の卒業生全員にこの本を配りました。

ジェームス・ワットの蒸気機関の発明とともに生産手段が大規模化し産業革命が起こり貧富の差が拡大しました。その対極からマルクス主義が生まれました。生産手段を労働者が奪い取ったものの一握りの特権階級が生まれ大衆は貧しいままとなりました。どちらも「人を幸せ」にする事ができませんでした。資本主義にも社会主義にも希望を見出せなくなったヨーロッパの人々は、自分達を幸せに導いてくれる次なる「イズム」を求めていました。その人々のの心の空白の中にヒトラーが提唱する国家社会主義「ファッシズム」が忍び寄りました。大変な災禍が生まれました。その帰結としてドラッガーは「人を幸せ」にするものとして「組織」に求めました。現代人は大部分が「組織」に属します。人を幸せにする現代社会の組織の「マネジメント」に答えを求めました。
政府の高官である父とオーストラリア・ハンガリー帝国で初めて医学教育を受けた母の家庭にはサロンとして錚々たる文化人が集まっていました。精神学者のジークムント・フロイトや後の20世紀を代表する経済学者になるヨーゼフ・シュンペーター、作家のトーマス・マン等です。マックス・トウラン・トラウネック伯爵とウィーン国立劇場の幹部女優兼演出家のマリア・ミュラーもクリスマスと元日にはドラッガー家を訪問しマリア・ミュラーは皆にせがまれ必ず詩の朗読と暗誦をしていました。トウラン伯爵は何時も目立たぬ様に部屋の隅でマリア・ミュラーを見つめていました。伯爵の左半身は無惨でした。
アルプスの峰の初ルートに挑戦中、山岳事故で半身に大きなダメージを受けてたトウラン伯爵に大きな敬意を両親が抱いていることを知ります。多くを語らないトウラン伯爵(国立図書館長)でしたが偶然にドラッガーが国立図書館で社会主義の二冊のパンフレットをみつけます。当時若きドラッガーは法哲学と社会学の本を読み漁っていました。一冊は著者名は「カール・ラウント」と記されておりトウラン伯爵のペンネームでした。カールは彼のクリスチャンネームでトウランの「t」の文字を後ろに移動させたネームがラウントでした。偶然その部屋に入ってきたトウラン伯爵は突き動かされた様に語り始めます。
・・そもそも伯爵なるものが、社会主義者だった事を変に思うかも知れない。でも、あの頃は誰もが社会主義者だったんだ。私は他の人たちよりも少し行動的だったかもしれない・・
・・でも当時は皆が社会主義こそが新しい社会を作るものと思っていた。マルクスを読んだものはほとんどいなかった。経済学に関心あるものもほとんどいなかった。私たちが関心のあったのは平和だった・・
・・その上すでに社会主義運動があった。キリスト教の誕生以来最大の大衆運動だった。しかもフランス、イタリア、ドイツ、オーストリア、そしてロシアには、それぞれの最大の政党、唯一の大政党として社会党があった。社会主義運動にも規律があった。ストライキも経験していた。その社会主義が平和を約束していた。私たちは社会主義者になったのだった・・
・・しかし、私たちの集まりは非公式で、組織も規約も名簿もなかった。皆が誰が仲間ということだけ知っていた。当時のヨーロッパは小さかった。教育ある若者は皆知り合いだった。山にも一緒に登った。家庭のパーティにも一緒に行った・・
・・今では第一次大戦は、軍人や外交官や産業界のせいにするのが流行っている。確かに彼らは馬鹿だった。しかし、本当に戦争を望んだのは、偉大なる社会主義大衆だったんだ。彼ら自身が戦争を煽り立てたんだ。ジャン・ジョレスが心配した様に、ヨーロッパ全体を戦争に巻き込んでしまったんのだ。そして社会主義自体も死んでしまった・・
・・君にはまだよくわからないかもしれないが、あの戦争の最大の罪は、ヨーロッパを台無しにしたことではないんだ。台無しにされたヨーロッパを救うべき人たちを殺してしまったことなんだ。リーダーになるべき人を全部殺してしまった・・
・・私が行ったイギリスのパブリックスクールでは同級生が48人いた。生き残っているのは18人しかいない。あとはフランダースの墓に眠っている・・
・・君のグレタ叔母さんの連れ合いのハンス叔父さんには兄弟が三人いた。そう言っては何だが、三人ともハンス叔父さんよりずっと優秀な人たちだった。でもそのうち二人は君のお母さんの従兄のアルニモと一緒にイタリアのチロルに埋められている。そしてハンス叔父さんのもう一人の弟エルンストは、ロシアで地雷にやられて、今ではイエズス会で皿を洗っている。元々は電気通信の天才だった・・
トウラン伯爵の話の後に「イギリスの悲劇」と言う一文がありました。
・・・今日では、イギリスの凋落はビクトリア朝ないしエドワード朝初期に始まったとされる。だがその最大の要因は指導層の多くが第一次大戦で殺され生き残った者も気力を失ったことにある。イギリスほど若い将校が死んだ国はなかった。他の国には、イギリスにおけるものほど無鉄砲を要求する紳士道を要求する国はなかった。
イギリスには教育のある若者がいなくなってしまった。共に育った二十代の乙女の淋しさを訴えて、ヴェラ・ブリテンの「若き者たちの残せし言葉」の右に出るものはない。第一次世界大戦が始まった時、ウィストン・チャーチルは既に四十代だった。そのため幸い免疫力がついていた。しかし次の世代、アンソニー・イーデンやハロルド・マクミラン(何も後のイギリスの首相)は癒えることのない傷を持って戦場から帰還していた。
イギリスが最も傷ついたのは支配階層が一つしかないことが起因していた。フランスにはアンシャン・レジーム(旧体制)の支配層と、ナポレオン以降のブルジョア体制のそれとの亀裂があった。その為国が期待すべき単一のリーダー層というものが存在しなかった。
同じように、ドイツでも競い合う支配階層があった。社会的な地位はあるが金のないユンカー、社会的な地位はないが金のあるブルジョワ、さらに自由業や学者が支配権を巡ってせめぎ合い、いずれもその地位を得るには至ってなかった。
ところが、イギリスにはただ一つの支配階層があった。しかもそれは、名門の貴族、田舎の地主、自由業の倅、実業家の孫など誰でも入れる階層だった。しかも、その階層に属さずその階層のように行動をすることを望まぬものまでが、その紳士なる階層の支配権を正当なものとして認めていた。
したがってこの階層が大量に失われ、かろうじて残った者が自信を喪失した時、そこに生じたのは完全な空白だった。その空白は、今日に至るも埋められていない。ヨーロッパの他の国々では、ビクトリア朝時代のイギリスに比べはるかに階層意識が強かった・・・しかしこの支配層が大量に死に、あるいは傷を負った時、支配層が一つしかなかったと言うことがイギリスの致命傷になった。
フランスでは、知的な訓練を受けたグランゼコールの卒業生たるテクノラートがリーダー層の地位に入り込んできた。ドイツでは企業の役員、労組の役員が正当なリーダー層として新たに登場した。ところがイギリスでは、第一次大戦が破壊したそれに代るべき層、その支配を認めうる層、自ら責任を負う層は現れなかった・・
(「ドラッガー 我が軌跡 知の巨人の秘められた交流」P.Fドラッガー著より)