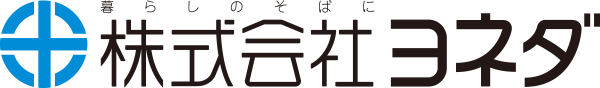8月17日の豪雨で被災された方々に心よりお見舞いを申し上げます。
又、弊社に賜りました多数の皆様からのお見舞い、応援に深く感謝申し上げます。
前日の16日は京都の北の方へ母の叔母のお墓参りに行っておりました。
その直後、京都市内から八木辺りまでものすごい豪雨となりました。
瑞穂町辺りまで来ると川の水量も少なく、
「ここいら辺は、余りふってないね。」
などと言いながら帰ってきました。
夕刻雷がひどく鳴っておりました。
夕食を食べだすと子会社の砂利採取会社のO工場長から「川筋に置いてある重機が水没しないか?」心配して電話があり、一旦は
「大丈夫やろ。川の水量も少なかったし・・。」
などと言っておりましたが、国土交通省のライブカメラを見ますと不気味な水量に見え
「やっぱり上げよか。直ぐ行くわ。」
と現地へ直行しました。
何とかトレーラー、台車を3台用意して高台にあるF重機さんの工場に上げさせていただきました。
2300頃帰宅し少しワインを飲んで2430頃就寝しました。
朝500前に電話の着信のランプや玄関のモニターホン人が訪ねて来た形跡に気づき大変なことになっている事に気づきました。
電話は0150に同じ建設業協会の副会長さんから、訪ねて来た人は近所に住む息子さんでした。
会社も市内のショールームも水没しました。。
やっと片付けが一段落したところです。
危機に瀕しても、「自分だけは大丈夫」と心のバランスをとろうとすることを「正常化の偏見」と言うそうです。
数日前に娘が夏休みで旅行をして帰路福知山へ立ち寄りそう言ってました。
彼女が北海道に帰った日に何気なく勤務する新聞社の電子版を覗くと「地方版記者コラム」にその事の小文を彼女が書いておりました。
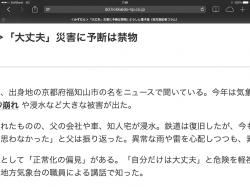
・・・2週間がたって感心していることは、道路のゴミや泥が概ね無くなっていることです。行政の方や業界の方、ボランテイア、自治会の方々等々ご尽力の結果と思っております。
・・・興味深かったのは掃除掃除で明け暮れた1週間目の日曜日の社員の過ごし方でした。
お客さまのお宅の床下にもぐりこみ、水で浸かった断熱材をとるという過酷な作業をやり続けたM君は
「2400に寝て400に起きて魚釣りに行きました。よう自分でも起きれたと思います。どうしても行きたかったので・・・。1500から今朝まで寝続けました。」
それを聞いたTさんは
「朝家の廻りを片付けて、それから終日飲んでたで・・・。」
と言うことでした。
私も朝起きてから暗くなるまで、以前読んでもう一度読みたいと思った本を読んでました。
若き佐藤優氏が外交官として在ソ日本大使館で内政調査に従事しロシア人と人脈を作り、ソビエト連邦消滅の歴史の渦を目の当たりにする秀作です。
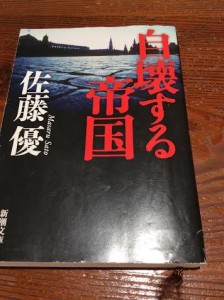
これも心のバランスをとろうとする代償行動みたいなものでしょうか?