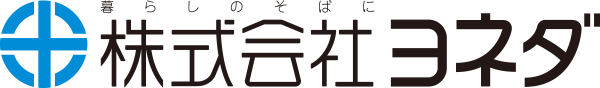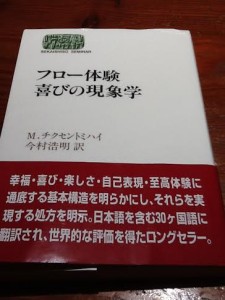新年、明けましておめでとうございます。
ご家族お揃いで輝かしい新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。
本年も何卒宜しくお願い申し上げます。
「・・・まあだだよ・・・♪」
の可愛い声。
見てみるとフェンスの向こうでお隣のお孫さんがかくれんぼ。
今年も穏やかな年であることを祈っております。
大学での伝説と言われるスピーチが載ってました。とても素晴らしかったのでシェアさせて頂きます。
世界でもっとも優秀な大学の卒業式に同席できて光栄です。私は大学を卒業したことがありません。実のところ、きょうが人生でもっとも大学卒業に近づいた日です。本日は自分が生きてきた経験から、3つの話をさせてください。たいしたことではない。たった3つです。
まずは、点と点をつなげる、ということです。
私はリード大学をたった半年で退学したのですが、本当に学校を去るまでの1年半は大学に居座り続けたのです。ではなぜ、学校をやめたのでしょうか。
私が生まれる前、生みの母は未婚の大学院生でした。母は決心し、私を養子に出すことにしたのです。母は私を産んだらぜひとも、だれかきちんと大学院を出た人に引き取ってほしいと考え、ある弁護士夫婦との養子縁組が決まったのです。ところが、この夫婦は間際になって女の子をほしいと言いだした。こうして育ての親となった私の両親のところに深夜、電話がかかってきたのです。「思いがけず、養子にできる男の子が生まれたのですが、引き取る気はありますか」と。両親は「もちろん」と答えた。生みの母は、後々、養子縁組の書類にサインするのを拒否したそうです。私の母は大卒ではないし、父に至っては高校も出ていないからです。実の母は、両親が僕を必ず大学に行かせると約束したため、数カ月後にようやくサインに応じたのです。
そして17年後、私は本当に大学に通うことになった。ところが、スタンフォード並みに学費が高い大学に入ってしまったばっかりに、労働者階級の両親は蓄えのすべてを学費に注ぎ込むことになってしまいました。そして半年後、僕はそこまで犠牲を払って大学に通う価値が見いだせなくなってしまったのです。当時は人生で何をしたらいいのか分からなかったし、大学に通ってもやりたいことが見つかるとはとても思えなかった。私は、両親が一生かけて蓄えたお金をひたすら浪費しているだけでした。私は退学を決めました。何とかなると思ったのです。多少は迷いましたが、今振り返ると、自分が人生で下したもっとも正しい判断だったと思います。退学を決めたことで、興味もない授業を受ける必要がなくなった。そして、おもしろそうな授業に潜り込んだのです。
とはいえ、いい話ばかりではなかったです。私は寮の部屋もなく、友達の部屋の床の上で寝起きしました。食べ物を買うために、コカ・コーラの瓶を店に返し、5セントをかき集めたりもしました。温かい食べ物にありつこうと、毎週日曜日は7マイル先にあるクリシュナ寺院に徒歩で通ったものです。
それでも本当に楽しい日々でした。自分の興味の赴くままに潜り込んだ講義で得た知識は、のちにかけがえがないものになりました。たとえば、リード大では当時、全米でおそらくもっとも優れたカリグラフの講義を受けることができたました。キャンパス中に貼られているポスターや棚のラベルは手書きの美しいカリグラフで彩られていたのです。退学を決めて必須の授業を受ける必要がなくなったので、カリグラフの講義で学ぼうと思えたのです。ひげ飾り文字を学び、文字を組み合わせた場合のスペースのあけ方も勉強しました。何がカリグラフを美しく見せる秘訣なのか会得しました。科学ではとらえきれない伝統的で芸術的な文字の世界のとりこになったのです。
もちろん当時は、これがいずれ何かの役に立つとは考えもしなかった。ところが10年後、最初のマッキントッシュを設計していたとき、カリグラフの知識が急によみがえってきたのです。そして、その知識をすべて、マックに注ぎ込みました。美しいフォントを持つ最初のコンピューターの誕生です。もし大学であの講義がなかったら、マックには多様なフォントや字間調整機能も入っていなかったでしょう。ウィンドウズはマックをコピーしただけなので、パソコンにこうした機能が盛り込まれることもなかったでしょう。もし私が退学を決心していなかったら、あのカリグラフの講義に潜り込むことはなかったし、パソコンが現在のようなすばらしいフォントを備えることもなかった。もちろん、当時は先々のために点と点をつなげる意識などありませんでした。しかし、いまふり返ると、将来役立つことを大学でしっかり学んでいたわけです。
繰り返しですが、将来をあらかじめ見据えて、点と点をつなぎあわせることなどできません。できるのは、後からつなぎ合わせることだけです。だから、我々はいまやっていることがいずれ人生のどこかでつながって実を結ぶだろうと信じるしかない。運命、カルマ…、何にせよ我々は何かを信じないとやっていけないのです。私はこのやり方で後悔したことはありません。むしろ、今になって大きな差をもたらしてくれたと思います。
2つ目の話は愛と敗北です。
私は若い頃に大好きなことに出合えて幸運でした。共同創業者のウォズニアックとともに私の両親の家のガレージでアップルを創業したのは二十歳のときでした。それから一生懸命に働き、10年後には売上高20億ドル、社員数4000人を超える会社に成長したのです。そして我々の最良の商品、マッキントッシュを発売したちょうど1年後、30歳になったときに、私は会社から解雇されたのです。自分で立ち上げた会社から、クビを言い渡されるなんて。
実は会社が成長するのにあわせ、一緒に経営できる有能な人材を外部から招いたのです。最初の1年はうまくいっていたのですが、やがてお互いの将来展望に食い違いがでてきたのです。そして最後には決定的な亀裂が生まれてしまった。そのとき、取締役会は彼に味方したのです。それで30歳のとき、私は追い出されたのです。それは周知の事実となりました。私の人生をかけて築いたものが、突然、手中から消えてしまったのです。これは本当にしんどい出来事でした。
1カ月くらいはぼうぜんとしていました。私にバトンを託した先輩の起業家たちを失望させてしまったと落ち込みました。デビッド・パッカードやボブ・ノイスに会い、台無しにしてしまったことをわびました。公然たる大失敗だったので、このまま逃げ出してしまおうかとさえ思いました。しかし、ゆっくりと何か希望がわいてきたのです。自分が打ち込んできたことが、やはり大好きだったのです。アップルでのつらい出来事があっても、この一点だけは変わらなかった。会社を追われはしましたが、もう一度挑戦しようと思えるようになったのです。
そのときは気づきませんでしたが、アップルから追い出されたことは、人生でもっとも幸運な出来事だったのです。将来に対する確証は持てなくなりましたが、会社を発展させるという重圧は、もう一度挑戦者になるという身軽さにとってかわりました。アップルを離れたことで、私は人生でもっとも創造的な時期を迎えることができたのです。
その後の5年間に、NeXTという会社を起業し、ピクサーも立ち上げました。そして妻になるすばらしい女性と巡り合えたのです。ピクサーは世界初のコンピューターを使ったアニメーション映画「トイ・ストーリー」を製作することになり、今では世界でもっとも成功したアニメ製作会社になりました。そして、思いがけないことに、アップルがNeXTを買収し、私はアップルに舞い戻ることになりました。いまや、NeXTで開発した技術はアップルで進むルネサンスの中核となっています。そして、ロレーンとともに最高の家族も築けたのです。
アップルを追われなかったら、今の私は無かったでしょう。非常に苦い薬でしたが、私にはそういうつらい経験が必要だったのでしょう。最悪のできごとに見舞われても、信念を失わないこと。自分の仕事を愛してやまなかったからこそ、前進し続けられたのです。皆さんも大好きなことを見つけてください。仕事でも恋愛でも同じです。仕事は人生の一大事です。やりがいを感じることができるただ一つの方法は、すばらしい仕事だと心底思えることをやることです。そして偉大なことをやり抜くただ一つの道は、仕事を愛することでしょう。好きなことがまだ見つからないなら、探し続けてください。決して立ち止まってはいけない。本当にやりたいことが見つかった時には、不思議と自分でもすぐに分かるはずです。すばらしい恋愛と同じように、時間がたつごとによくなっていくものです。だから、探し続けてください。絶対に、立ち尽くしてはいけません。
3つ目の話は死についてです。
私は17歳のときに「毎日をそれが人生最後の一日だと思って生きれば、その通りになる」という言葉にどこかで出合ったのです。それは印象に残る言葉で、その日を境に33年間、私は毎朝、鏡に映る自分に問いかけるようにしているのです。「もし今日が最後の日だとしても、今からやろうとしていたことをするだろうか」と。「違う」という答えが何日も続くようなら、ちょっと生き方を見直せということです。
自分はまもなく死ぬという認識が、重大な決断を下すときに一番役立つのです。なぜなら、永遠の希望やプライド、失敗する不安…これらはほとんどすべて、死の前には何の意味もなさなくなるからです。本当に大切なことしか残らない。自分は死ぬのだと思い出すことが、敗北する不安にとらわれない最良の方法です。我々はみんな最初から裸です。自分の心に従わない理由はないのです。
1年前、私はがんと診断されました。朝7時半に診断装置にかけられ、膵臓(すいぞう)に明白な腫瘍が見つかったのです。私は膵臓が何なのかさえ知らなかった。医者はほとんど治癒の見込みがないがんで、もっても半年だろうと告げたのです。医者からは自宅に戻り身辺整理をするように言われました。つまり、死に備えろという意味です。これは子どもたちに今後10年かけて伝えようとしていたことを、たった数カ月で語らなければならないということです。家族が安心して暮らせるように、すべてのことをきちんと片付けなければならない。別れを告げなさい、と言われたのです。
一日中診断結果のことを考えました。その日の午後に生検を受けました。のどから入れられた内視鏡が、胃を通って腸に達しました。膵臓に針を刺し、腫瘍細胞を採取しました。鎮痛剤を飲んでいたので分からなかったのですが、細胞を顕微鏡で調べた医師たちが騒ぎ出したと妻がいうのです。手術で治療可能なきわめてまれな膵臓がんだと分かったからでした。
人生で死にもっとも近づいたひとときでした。今後の何十年かはこうしたことが起こらないことを願っています。このような経験をしたからこそ、死というものがあなた方にとっても便利で大切な概念だと自信をもっていえます。
誰も死にたくない。天国に行きたいと思っている人間でさえ、死んでそこにたどり着きたいとは思わないでしょう。死は我々全員の行き先です。死から逃れた人間は一人もいない。それは、あるべき姿なのです。死はたぶん、生命の最高の発明です。それは生物を進化させる担い手。古いものを取り去り、新しいものを生み出す。今、あなた方は新しい存在ですが、いずれは年老いて、消えゆくのです。深刻な話で申し訳ないですが、真実です。
あなた方の時間は限られています。だから、本意でない人生を生きて時間を無駄にしないでください。ドグマにとらわれてはいけない。それは他人の考えに従って生きることと同じです。他人の考えに溺れるあまり、あなた方の内なる声がかき消されないように。そして何より大事なのは、自分の心と直感に従う勇気を持つことです。あなた方の心や直感は、自分が本当は何をしたいのかもう知っているはず。ほかのことは二の次で構わないのです。
私が若いころ、全地球カタログ(The Whole Earth Catalog)というすばらしい本に巡り合いました。私の世代の聖書のような本でした。スチュワート・ブランドというメンロパークに住む男性の作品で、詩的なタッチで躍動感がありました。パソコンやデスクトップ出版が普及する前の1960年代の作品で、すべてタイプライターとハサミ、ポラロイドカメラで作られていた。言ってみれば、グーグルのペーパーバック版です。グーグルの登場より35年も前に書かれたのです。理想主義的で、すばらしい考えで満ちあふれていました。
スチュワートと彼の仲間は全地球カタログを何度か発行し、一通りやり尽くしたあとに最終版を出しました。70年代半ばで、私はちょうどあなた方と同じ年頃でした。背表紙には早朝の田舎道の写真が。あなたが冒険好きなら、ヒッチハイクをする時に目にするような風景です。その写真の下には「ハングリーなままであれ。愚かなままであれ」と書いてありました。筆者の別れの挨拶でした。ハングリーであれ。愚か者であれ。私自身、いつもそうありたいと思っています。そして今、卒業して新たな人生を踏み出すあなた方にもそうあってほしい。
ハングリーであれ。愚か者であれ。(Stay Hungry. Stay Foolish.)
ありがとうございました。
(This is a prepared text of the Commencement address delivered by Steve Jobs, CEO of Apple Computer and of Pixar Animation Studios, on June 12, 2005.)日本経済新聞 電子版2015.1.2より