最近は、朝の楽しみが増えました。
日本経済新聞に連載されている、ノーベル化学賞受賞の下村脩さんの「私の履歴書」を読む楽しみです。
・・・下村さんのことは以前にもこのブログで触れました。
下村氏は軍人であった父上の勤務地の関係で、当地福知山で出生。お母さんの出身地の長崎県の諫早に疎開、長崎大学薬学部で学問の基礎を学ばれ、名古屋大学・プリンストン大学・ボストン大学で発光生物の研究の第一人者として活躍されました。
 (発光するGFE)
(発光するGFE)
各々の時代の師に導かれウミホタル・オワンクラゲ等の研究活動を通じ、発光生物の発光メカニズムを次々と解明。なかでもプリンストン大学時代にフライデーハーバー実験所で行ったオワンクラゲからのイクオリンおよび緑色蛍光タンパク質 (GFP) の発見は、医学臨床分野にも大きな影響を及ぼしているそうです。
・・・読んでいて、特に強く印象に残っているのは次の一文です。
(名古屋大学からフルブライト留学生として、プリンストン大学のフランク・ジョンソン教授に招請され渡米。「オワンクラゲの発光メカニズム」というテーマを与えられ「光るタンパク質」を発見し、大きな成果として帰国后・・・。)
「・・・気になっていたのは、私がオワンクラゲから発見した発光タンパク質のイクリオンのことだった。その発光メカニズムが分からないままだと、単なる奇妙なタンパク質に過ぎないことになる。
・・・米国に再び渡って、生物発光の研究に専念したいとの思いが募った。
ただ最初に訪米した時と事情は大きく違う。名古屋に戻った翌64年には、長男が生まれていた。・・・実際のところあと数年で教授にしてもらえるはずだった。一方米国に行くと、研究費を自分で獲得しなければならないので、研究を続けるのは大変なことである。
ほぼ3年ごとに研究費の申請をしなければならず、その更新に失敗すれば、即失業となる。厳しい競争会の中で、研究費を獲得していくのには困難が予想された。
妻に相談をすると「あなたの好きなようにして下さい」という返事だった。それで、米国に戻ることを決めた。米国東南部の大学からも招請があったが、結局、フランク・ジョンソン教授のいる古巣のプリンストン大学に行くことにした。
今考えると、ぞっとするくらい、リスクのある決断だった。それが出来たのは、私たち夫婦がまだ若かったのと、生物発光の研究を自らの手で進めたいという執念ゆえのことだった。」
日本経済新聞 2010年7月19日 朝刊


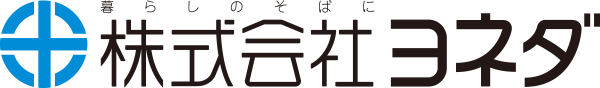






 (発光するGFE)
(発光するGFE)