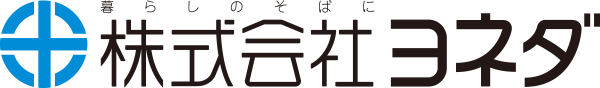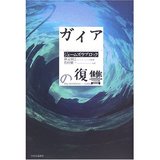
「社長昨夜の映画見ましたか?」(チーム・マイナス6%のメンバー)
「見たで・・。地球が急に(温暖化の反対の)氷河期になる映画やったけど・・ロサンゼルスがいくつもの竜巻に巻かれたりニュ-ヨークが大洪水になるシーンがあったけどああなるんかなぁ・・。」
「気候変動って恐ろしいなぁ・・。」
会社でそんなワンシーンがありました。
昨日、ジェームズ・ラブロック博士の「地球の逆襲」を読みました。好きな映画の「地球交響曲(ガイアシンホニー)4番」に出演され名前を知っていたため、たまたま本屋で手に取りました。
「地球の処方箋」と書いてありましたが温暖化の問題を「ガイア理論」の提唱者である博士が「惑星専門の医師」の立場から説いておられます。
「地球温暖化の熱が極めて有害な現実であり、人間や地球の制御出来る限度をすでに超えたかもしれないのに、それを理解できずにいるのはなぜだろう・・。」
「われわれはガイアを生物も非生物も含めた総合システムと考えなければならない。・・主流の生物にとって暑すぎる、あるは寒すぎる状況があるのは当然だが、海洋の表面温度が約12℃以上になると生命なき砂漠のような状態になると言う事実はあまり知られていない。・・海面近くに暖かい水の層が形成されるが、これはもっと冷たくて養分の豊富な下層の水とは混じらない。」
「海面と同様の、そして同じくらいの重要な個体数の増加への制約は地表にも働いている。生命体は約40℃までの暖かさなら繁栄するが、自然界では気温が20℃を大きく上回ると、生命維持に欠かせない水を手に入れるのが難しくなる。冬季に雨が降り、気温が10℃を下回ると、雨水はかなりの期間あちこちにとどまるし、土も湿ったままで個体数の増加に適する。しかし夏が来て平均気温が20℃近くになると、雨は新しく降っても直ぐに蒸発し、地表は乾いたままになる。雨が繰り返し頻繁に降らなければ、土は湿気を失う。気温が25℃を上回る場所では蒸発があまりに速いため、雨が続かなければ土は乾き、土地は砂漠化する。・・気温が4℃上昇すればアマゾンの森林はその力を失い、低木帯や砂漠に変わってしまうと示唆している。」
「・・そしてそれがどれほど深刻かを心に留めておくため、このグラフ(過去千年間の平均気温の変化)を目につく場所に貼っている。グラフは温度と自然のゆらぎを示しており、過去千年の最初の八百年間には、わずかだがそれとわかる下落傾向がある。それがもしはっきりした傾向になれば、氷河時代になることを示す。それが1850年頃の産業振興期の始まりにはゆっくり上昇し始め、かつてないほど加速して、長期平均で約1℃上がった。・・グラフの長期平均と一万二千年前の氷河時代との温度差は、3℃ちょっとである。IPCCの2001年の報告書は、「ホッケーステイック」グラフの線が今世紀の間にさらに5℃上がるだろうと示唆している。これは氷河時代から産業革命前までの温度変化の約2倍にあたる。」
「地球温暖化に直接的で大胆な答えは・・・。彼らは地球と太陽の間の宇宙空間に日除けを作ろうと提案したのである。」(「気候変動に対処するマクロ技術の選択肢」2004年 ケンブリッジ大)
「太陽の放射エネルギーの流入を減らすのと同じくらいに有望なのは、海洋面の広いエリアに海洋性の層雲を人工的に作る計画だ。・・コロラド洲にある国立大気研究センターのジョン・レイサムは、海水を雲の核になる微粒子のエアロゾルに変える、小型で実用的な装置について説明した。海藻が硫化ジメチルを放出して作り出した低高度の海洋性層雲が、自然の冷却に一役買っているということがすでに知られているからだ。」(同)
荒唐無稽(こうとうむけい)のようですが、真剣に論じられております。
社員のアンケートもこの本の一部を参考にしました。
少しづつ学んでいき実践していきたいと思います。
「地球はそれ自体が大きな生命体である。
全ての生命、空気、水、土などが有機的につながって生きている。
これをGAIA(ガイア)と呼ぶ。」
ジェームズ・ラブロック