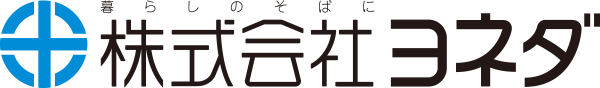先日より、何回か「風姿花伝」世阿弥著(竹本幹夫訳注)をパラリパラリと読み返しております。申楽(さるがく)と呼ばれる能の奥義を父観阿弥の遺訓をもとに子孫に伝えるべく世阿弥が著した芸術論です。
年来稽古条々
七 歳
一、この芸において、大方七歳をもて初めとす。・・・・ふとしいださんかかりを、うちまかせて心のままにせさすべし。さのみに、善き悪しきとは、教ふべからず。あまりにいたく諫むれば、童は気を失いて、能ものぐさくなりたちぬれば、やがて能はとまるなり。・・・・大場などの脇の申楽には立つべからず。三番・四番の、時分のよからんずるに、得たらん風体をせさすべし。
(偶然やり出した演じ方を干渉せずにやらせればよい。「良い」「悪い」と指導してはならない。・・・晴れの舞台の冒頭の能には出演してはならない。三番四番のちょうどよい潮時をみはからって、得意な演技をさせるがよい。)
十二三より
この年のころよりは、はや漸々声も調子にかかり、能も心づくころなれば、次第次第に物数も教ふべし。まづ童形なれば、なにをしたるも幽玄なり。声も立つころなり。二つの便りあれば、悪きことは隠れ、よきことはいよいよ花めけり・・・・さりながら、この花は真の花にはあらず。ただ時分の花なり。
(この年の頃より、次第に歌声も笛の調子に合うようになり、演技にも自覚が生じてくるころなので、だんだんいろいろな演目を教えるが良い。まずは稚児姿なのでどんな風にやっても愛らしい。歌声も華やかに目立つ頃である。この二つの利点があるので、欠点は隠れ、美点はいよいよ魅力的に見えるのだ。・・・・しかしながら、この花は、本物の芸の魅力ではない。単なるその時期の魅力である。)
十七八より
このころはまた、あまりの大事にて、稽古多からず。まづ声変りぬれば、第一の花失せたり・・・・・このころの稽古には、指をさして人に笑わるるとも、それをばかへりみず、内にて、声の届かんずる調子にて、宵暁の声を使ひ、心中には願力を起こして、一期のさかひここなりと、生涯にかけて、能を捨てぬよりほかは、稽古あるべからず。
(このころの稽古はあまりに大変なので、稽古の種類は多くない。まず、声変わりになるので、最も華やかな魅力であった少年期の歌声が失ってしまう・・・・この時期の稽古としては、たとえ人に指さされ笑われても、そんなことは意に介さず、家では声が無理なく出せるような調子で、夜間夜明けの謡稽古を行い、心の中では神仏に願をかけ、意志の力を奮い起こして、一生の分かれ目はここだと、我が生涯にかけて芸を捨てぬ以外には、稽古の方法はあるまい。)
二十四五
中略
三十四五
中略
四十四五
このころよりは、能のてだて、おほかた変わるべし。たとひ、天下に許され、能に徳法したりとも、それにつきても、よきわきのしてを持つべし。・・・・・このころよりは、さのみに、こまかなるものまねをばすまじきなり。おほかた似合たる風体を、やすやすと、骨を折らで、わきにしてに花を持たせて、あひしらひの様に、すくなすくなとすべし・・・・・もし、このころまで失せざらん花こそ、真の花にてはあるべけれ。
(この年頃からは芸の手立ては全く変わってしまうであろう。たとえ都で認められ、芸の奥義を体得していたとしても、それにつけても、優れた控えの役者をそばに置いておくのがよい・・・・この年頃からはあまり手の込んだ能をしてはならない。大体自分の年齢相応の能を、楽々と無理なく、二番手の役者に多くの演目を譲って、自分は添え物のような立場で控えめに出演するのがよい・・・・もしもこの頃までに無くならない芸の魅力があったなら、それこそが「本当の花」と言うことになろう。)
五十有余
中略
年来稽古条々 以上
芸術論だけでなく、人生論としても味わい深いですね。
五百年前にひとつの道の奥義を極めた世阿弥と言う人物が現代人に語りかけてくるものは何でしょうか?
現代の我々が(訳注の助けをかりながらも)、中世の稀有な人物の明晰な日本語での語りかけを味わえるのは幸せですね。