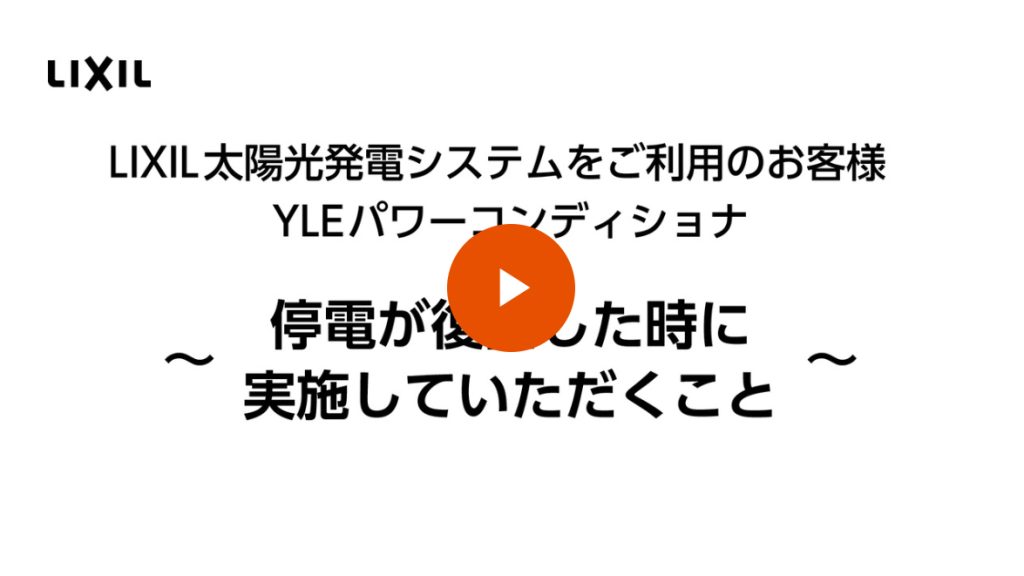水漏れ
水漏れの応急処置方法
水漏れが発生したら、まずは止水栓を閉めて水の流れを止めることが重要です。
次に、漏水箇所を特定して、修理方法を確認しましょう。
止水栓の閉め方
キッチン・洗面台の場合

シンク下の引き出しまたは開き戸を開けて
止水レバーを閉めます。
トイレの場合
トイレの横にある給水管の止水栓を
マイナスドライバーで締めます。

トイレ手洗いの場合

手洗い器下部のボックスを開け
マイナスドライバーで止水栓を閉めます。
浴室サーモ水栓の場合
水栓下の湯水の止水栓を
マイナスドライバーで締めます。

洗濯機の場合

洗濯機の給水栓を閉めます。
エコキュートの場合
エコキュートの下部カバーを外して
止水栓を閉めます。

水漏れの原因箇所の確認
水漏れの原因を特定するために、以下の手順を試してみましょう。
目視での確認

漏れていると思われる場所を拭き取り、水漏れが続いていないか確認します。
もし水漏れが続いている場合、その場所が漏水箇所である可能性が高いです。
水道メーターを使った確認

1.すべての水周りの止水栓を閉めて、水道メーターを確認します。
2.メーターが止まっていれば、建物内で漏水が発生していることがわかります。
3.水回りの止水栓を一つずつ開けていき、メーターが動くかどうか確認します。
4.メーターが動き出したら、開けた止水栓が漏水箇所です。
修理方法
一般的な水漏れ箇所の修理方法
- 蛇口やパッキンの劣化が多いです。ホームセンターで部品を購入して、簡単に取り替えることができます。
- ナットの緩みが原因で水漏れが発生している場合もありますので、ナットがしっかり閉まっているか確認してください。
もし自分で修理ができない場合や、原因が不明な場合は、ご連絡ください。
排水つまり
キッチンの排水つまり
つまりが起こる主な原因
- 油汚れ
- 食材のカス・ヌメリ
- 洗剤・石鹸カス
- 固形物が流れた
つまりを自分で直す方法
1.お湯を一気に流す

油汚れが原因の場合は、お湯を流し込むと解消する場合があります。シンクにお湯を溜め、一気に押し流すと効果が高まります。以下のような方法であれば、手軽に実践が可能です。
- 布やビニール袋を詰めて排水口をふさぐ
- 40℃以下のお湯を溜める
- 布やビニール袋を取り出す
- お湯が流れきるまで待つ
温度は40℃以下にとどめ、熱湯をかけないように注意してください。熱湯を流すと排水管が熱で変形し、劣化の原因につながります。
2.パイプクリーナーを使用する

パイプクリーナーとは、排水口に付着したつまりやヌメリを分解する効果を持つ洗剤です。薬局やスーパーなどで手軽に購入できるため、一度試してみてください。
3.ペットボトルを押し込む

空のペットボトルの先端を排水口にくっつけ、空気を送り込むとつまりが解消する可能性があります。具体的には、以下のステップで実践してみてください。
- 排水口のフタ・ゴミ受けを取る
- ゴミ受けの下にあるワントラップを取る
- 排水口にペットボトルを差し密着させる
- 空気を送るイメージでペットボトルをへこませる
- へこませる動作を10回以上実施する
- ペットボトルを引き抜く
キッチン排水口つまり予防方法
1.油汚れはペーパーで拭き取る
食器やフライパンなどに付着する油汚れは、水洗いをするとつまりの原因となります。そのため、ペーパーで拭き取り、排水口へ流さないことが大切です。
2.食材カスを排水口に流さない
食材カスを排水口に流すと、つまりの原因となります。水切りネットを使用すれば、細かい食材カスのキャッチが可能ですので、水切りネットの使用をおすすめします。
3.洗剤は適量の使用を心掛ける
洗剤を使い過ぎると、カスが蓄積されてつまりの原因となるため、必要以上に使い過ぎないことが大切です。
トイレの排水つまり

トイレの排水つまりの症状
- 水の流れが悪い
- 水を流すと水位が上がってくる
- 便器の中の水が少なく、異臭がする
- 異音がする
トイレの排水つまりの原因
- 水に溶けにくい物を流した
- 異物を流した
- 流す水の量が少ない
- 掃除不足で尿石が溜まっている
つまりを自分で治す方法
1.40℃~60℃のお湯を流す

トイレットペーパーのような水に溶ける物がつまっている場合に有効です。数回に分けてお湯を入れることでより溶けやすくなり、つまりを取り除けます。約一時間ほどで溶けます。
2.針金ハンガーを使用する

お家に針金ハンガーがあれば、そのハンガーを使用してみてください。
ハンガーを折り曲げ便器の中に入るように変形させ奥まで差し込みます。何かに当たれば異物になりますので数回押し、流れるようになるか確認します。
変形だけで異物に届かない場合はペンチなどでハンガ—をカットし細長くして、先を丸く輪っかを作ってください。
上記と同じ方法で異物が流れるか確認してください。
3.カバーラップを使用する

つまりが異物ではない場合、トイレットペーパーなどの水に溶けるものに有効です。ホームセンターで販売しているのですぐに手に入りやすいです。
勢いがすごいため、周りに汚水が飛散する恐れがあるのでビニールなどを床に敷くのをおすすめします。
便器内の水位が便器より10㎝以下になるようにし、カバーカップをゆっくり押し込んで密着させたら、勢いよく引っ張り上げます。スムーズに排水されるようになるまで、これを数回繰り返します。
つまりが取れたら、バケツなどでゆっくりと流し、スムーズに排水されるか確認してください。
異物を放置してはいけないもの

紙おむつやナプキン、尿漏れパッドなどの吸水性の物がトイレにつまった場合、早急に取り出すことが重要です。これらは水を吸って膨らみ、解消が難しくなります。
ラバーカップを使うと異物が奥に押し込まれる可能性があるため、無理に使わず、難しい場合はご相談ください。
停電・漏電
漏電とは

漏電の兆候
漏電とは、配線や電化製品から電気が外に漏れる現象です。通常は絶縁処理で防がれていますが、劣化や故障により漏電が起きると、火災や感電事故の危険があります。
漏電に気づく主な理由は停電です。頻繁に漏電ブレーカーが落ちる場合、漏電の可能性があります。他にも、電気代が急増したり、家電に水がかかった場合も注意が必要です。
「金属部分に触れるとビリビリする」「雨で停電する」「家電から水漏れ」などの症状があれば、漏電の可能性が高いので注意が必要です。
漏電の発生原因とは

漏電の主な原因は、配線や家電、建物の経年劣化です。塩害による配線の腐食や、小動物が配線をかじることも要注意!
また、コンセントにプラグが不完全に刺さっている場合や、タコ足配線も漏電を招く可能性があります。
漏電場所の確認方法

漏電している回路を特定する方法
ブレーカーは漏電していると分電盤にある漏電ブレーカーが落ちる仕組みになっています。これを使って特定しましょう。
1. すべての安全ブレーカーをオフにします。
2. 漏電ブレーカーをオフにして、電流を遮断したらオンにします。
3. 安全ブレーカーを1つずつオンにします。
4. オンにして漏電ブレーカーが落ちなければ正常ですが、落ちたらその箇所で漏電しています。
漏電箇所を特定する方法
漏電している箇所が判明したら、その部屋にある家電製品のプラグをすべて抜き、『漏電している回路を特定する方法』と同じ手順を繰り返します。
この方法で漏電ブレーカーが落ちなければ家電製品に問題があります。
停電時の太陽光への切り替え方
太陽光発電システムは、停電時でも「自立運転機能」により、発電時は一定量の電気を使うことができます。
自立運転にするためには切り替え操作が必要です。

停電が復旧した際は、「自立運転」から「連系運転」への切り替えが必要です。
忘れず行ってください。